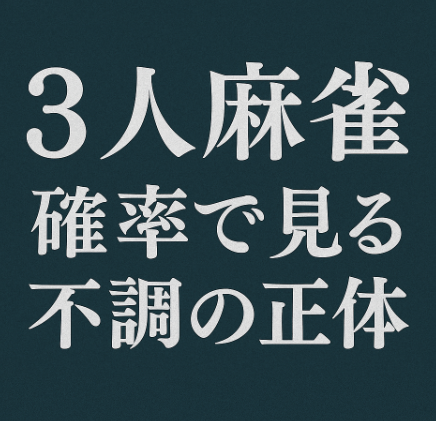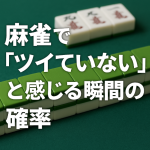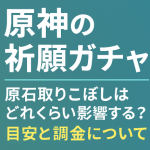麻雀を打っていると、「今日はどうして自分だけこんなにツイていないんだろう」と感じる瞬間は誰にでもあります。ラスが続く、トップが一度も取れない、リーチしても裏ドラがまったく乗らない――。こうした“不運の連鎖”は、実力や判断力に自信があっても心を折る原因になります。
前回の記事では、標準的な4人麻雀(ヨンマ)を前提に、代表的な「ツイていない」と感じる現象を確率で整理しました。例えば連続ラスの確率は、2回で6.25%、3回で1.56%。裏ドラ不発も単発で約6割以上の確率で起こり、連続で空振りすることも決して珍しくないことが見えてきました。数字で裏付けしてみると、私たちが「理不尽だ」と感じている出来事は、実は想定内の範囲に収まっているのです。
では、プレイヤー数が一人少なく、展開が激しいとされる3人麻雀――特にオンライン麻雀で多くの人が遊んでいる雀魂のサンマルールではどうでしょうか。萬子の2~8を抜き、北抜きが存在する108枚の牌山。リーチ後には裏ドラがあり、赤5も入るため打点の振れ幅は大きく、ヨンマ以上に荒れやすいゲーム性です。この環境下では「不運」に思える現象はどのくらいの頻度で起こるのか。ヨンマとの違いを数値で比べると、サンマ特有の厳しさが見えてきます。
まず単純にプレイヤー数が3人になるだけで、ラス率は25%から33.3%へと増加します。つまり「ラスを引くのは当たり前に近い」確率になり、連続ラスの発生率も跳ね上がります。さらにトップ率も同じ33.3%しかないため、「トップを取れない連続」の確率はヨンマ以上に高く、感覚的に「勝っている実感がない」日が生まれやすいのです。裏ドラに関しても、牌山が108枚になることで確率は微妙に変動し、単発不発の確率はヨンマよりわずかに下がるものの、それでもおよそ6割前後。やはり「裏ドラは基本的に乗らない」と考えるのが正解です。
本記事では、前回の4人麻雀での数値を振り返りつつ、雀魂の3人麻雀を前提に「連続ラス」「トップ不在の連続」「裏ドラ不発」という3つの現象を改めて確率で整理します。ヨンマと比べてどのくらい違うのかを確認することで、「サンマは荒れるゲーム」という漠然とした印象を数字で裏付けられるはずです。確率を知っておけば、不運の渦中にあっても「これは誰にでも起こる」と冷静に受け止めることができます。
連続ラスを引く確率 ― 4人麻雀との違い
麻雀で一番精神的にこたえる結果といえば「ラスを引き続けること」です。1回ラスを取るだけでも気持ちは沈みますが、2回・3回と続けば「今日はもうダメだ」「実力が足りないのでは」と自信を失いがちです。前回の記事では4人麻雀を前提に計算しましたが、雀魂サンマに切り替えるとこの確率は大きく変わってきます。

まずラス率の基本が違います。4人麻雀ではラスを引く確率は1/4=25%ですが、サンマでは3人中1人がラスになるので1/3=33.3%。この時点で単発ラスの可能性がぐんと高いのです。「ラスは3人に1人が背負うもの」と考えれば、サンマでラスを取るのは特別ではなく“日常的に訪れる結果”だと分かります。
では連続ラスに注目してみましょう。独立試行の近似で「連続ラス確率」を求めると、4人麻雀とサンマでは次のような差が出ます。
- 2連続ラス
ヨンマ:6.25%(16回に1回)
サンマ:11.1%(9回に1回) - 3連続ラス
ヨンマ:1.56%(64回に1回)
サンマ:3.7%(27回に1回) - 4連続ラス
ヨンマ:0.39%(256回に1回)
サンマ:1.23%(81回に1回) - 5連続ラス
ヨンマ:0.097%(1,024回に1回)
サンマ:0.41%(243回に1回)
数字を並べてみると一目瞭然です。ヨンマでは256半荘に1回レベルの「4連ラス」が、サンマでは81半荘に1回。つまり同じくらい打っていれば、サンマの方が圧倒的にラス連鎖を踏む可能性が高いのです。3連続ラスを例に取っても、ヨンマの64分の1に対してサンマは27分の1。月に数十半荘打つ人ならほぼ毎月遭遇してもおかしくない頻度です。
ここで大事なのは「連続ラスが起きる確率はサンマでは十分高い」という事実を知ることです。2連続ラスは9回に1回、3連続ラスは27回に1回。これを“特別な不運”と捉えると精神的に辛くなりますが、実際は「誰でも定期的に踏むもの」なのです。むしろラスが連続するのは“ゲームの仕様”に近いと割り切った方が気が楽になります。
また、心理的な影響も見逃せません。2連続ラスを引いた時点で「次もラスだったらどうしよう」と不安が膨らみ、結果として守りすぎたり、逆に無理に攻めて失敗したりします。統計的には数%の出来事でも、体験している本人には「呪われている」としか思えず、さらにミスを誘発して連鎖を長引かせてしまうのです。
だからこそ、数字を知っておくことは武器になります。サンマで3連続ラスを引いても「27回に1回なら十分あり得る」と納得できれば、焦りを抑えて冷静に次局へ臨めます。ラス連鎖の本当の恐ろしさは「確率そのもの」ではなく、「それに振り回されて打ち方が崩れること」なのです。
トップを取れない確率 ― 4人麻雀との比較で分かるサンマの厳しさ
麻雀で「今日は全然勝っている実感がない」と感じる瞬間は、ラスを引かなくても訪れます。そう、トップがまったく取れない日です。点棒を減らさず2着を積み重ねていても、トップが遠ざかると気分的には「勝っていない」と思いやすいものです。前回は4人麻雀を前提に「連帯できない確率」を整理しましたが、今回はサンマの「トップを取れない連続確率」をヨンマと比較してみましょう。

まず基本の単発確率から。ヨンマではトップ率は25%なので「トップを取れない確率」は75%。一方でサンマは3人中1人しかトップになれないため、トップ率は33.3%、つまり「トップ不在の確率」は66.7%です。一見するとヨンマの方がトップを逃しやすいように思えますが、実はここが大きな誤解ポイント。ヨンマでは「トップを逃す」=2位・3位・4位の広い分布であり、特にラス(4位)を避けられることも多いので心理的ダメージは分散されます。サンマの場合は2位も3位も「トップを取れなかった」という同じ扱いになりやすく、体感的にはヨンマ以上にトップ欠乏を強く感じます。
数字を並べて比較してみましょう。
- 1回トップを逃す
ヨンマ:75%
サンマ:66.7% - 2連続トップなし
ヨンマ:56.3%(約2回に1回)
サンマ:44.4%(約2回に1回より少し軽い) - 3連続トップなし
ヨンマ:42.2%(約2回に1回弱)
サンマ:29.6%(約3回に1回) - 4連続トップなし
ヨンマ:31.6%
サンマ:19.8% - 5連続トップなし
ヨンマ:23.7%
サンマ:13.2%
このように計算上は「トップを逃す確率」そのものはヨンマの方が高く出ます。サンマは母数が3人しかいない分、トップを取れる確率も33.3%とやや高く、結果的に“トップなしの連続率”はヨンマより低めになるのです。
ところが、ここで重要なのは数字以上に「心理的な体感」です。サンマは順位点(雀魂なら +30/0/-30)が大きく、トップを取らないとプラスが得られにくいルールです。つまり理論上はヨンマより「トップを逃す確率」が低くても、実利面では「トップを取れない日=負けている日」と直結しやすいのです。ヨンマなら2位を積み重ねて安定したプラスにできる場面でも、サンマでは2位が続いてもポイントは伸びず、モチベーションを削がれやすい。
このズレこそが「サンマはトップが取れないと苦しい」と感じる理由です。確率上はヨンマよりマシなはずなのに、ゲーム設計上トップの価値が極端に大きいため、3連続トップ不在(約30%)にでも遭遇すれば「今日は全然勝てない」と実感するのです。
したがって、サンマにおいては「トップを取るのが難しいのではなく、トップを取らないと意味が薄い」という性質を理解することが大切です。トップ欠乏に出会ったときに「これは3割弱の確率で普通に起こる範囲」と割り切れば、余計な焦りを抑えて打てます。逆に「トップを取らねば」と焦って無理に攻めるとラス転落のリスクが跳ね上がり、長期的に損をするでしょう。
裏ドラが「乗らない」確率 ― 雀魂サンマ(北抜きあり)とヨンマの比較

「せっかくリーチしたのに裏が全然乗らない」――体感的には“かなり起きる”出来事ですが、数字で見るとどうでしょう。ここでは 雀魂サンマ(萬子2〜8抜き/北抜きあり/牌山108枚) を前提に、まずは最もシンプルなケース(裏指示1枚・カンなし)で近似します。考え方は「リーチ時点の手牌13枚に、裏ドラの種類(同一種類4枚)が1枚も含まれていない確率」です。計算はハイパージオメトリックの近似で、
- サンマ(108枚)
不発(乗らない) ≒ C(108−4, 13) / C(108, 13) ≈ 59.4%
→ 裏が「乗る」 ≈ 40.6% - 参考:ヨンマ(136枚)
不発 ≈ 62%強、乗る ≈ 38%弱
つまり、牌山が小さいサンマの方が “わずかに”裏が当たりやすい(不発がやや減る)傾向です。ただし“体感的にはしょっちゅう外れる”のは事実で、単発でも 約6割は外れる という理解でOKです。
ここから連続事象を見てみます(独立試行近似):
- 2回連続で裏ドラ不発:0.594² ≈ 35.3%
- 3回連続で不発:0.594³ ≈ 21.0%
- 4回連続で不発:0.594⁴ ≈ 12.45%
- 5回連続で不発:0.594⁵ ≈ 7.40%
南1〜南4の4回すべてでリーチし、全部外れる 可能性は 約12.5%(8回に1回強)。印象より“普通にあり得る”レンジです。ヨンマでも「単発不発が約62%」なので、連続外しの確率はサンマより 少しだけ 高くなりますが、体感差は小さめです。
注意点と前提を補足します:
- 北抜きの影響:抜いた北は山からも可視領域からも離れ、都度補充が入るため「見えない牌の総数」が減ります。厳密に追跡すると裏ヒット率は状況依存で微妙に上下しますが、ここでは平均化して 「108枚前提の近似」 としました。実戦では北の抜かれ方(枚数・タイミング)で数%単位のブレが出ます。
- カン/裏指示の増加:暗槓・加槓で裏指示が増えれば「どれか1枚でも当たる」確率は当然上がります。本稿の表は 裏指示1枚 前提の“保守的な目安”です。
- 赤ドラは無関係:赤はドラ表示ではないため裏の当たり外れには直接影響しません(打点の揺れには影響)。
- 実戦バイアス:手作りの方針(対子場・染め・字牌の多寡)や副露進行により、リーチ時点での「手牌13枚に特定種類を含む率」は上下します。ここでは多くの局面を平均化した ざっくり値 としています。
まとめると――
サンマでもヨンマでも 「裏はだいたい乗らない(単発で約6割不発)」。サンマは山が小さいぶんわずかに当たりやすいものの、感覚を変えるほどではありません。4回連続不発が 約12.5% もあると知っていれば、「南場で全部外れた…今日は呪われてる?」という場面でも「統計的には普通にある」と受け止めやすくなります。裏に依存しない打点設計(裏なしでも満貫到達、打点の底上げを先に作る)を心がけることで、“裏ブレ”の日でも成績の振れ幅を抑えられます。
まとめ ― 雀魂サンマで「ツイていない確率」を考える
ここまで見てきたように、前回の4人麻雀の記事と比較すると、雀魂の3人麻雀(萬子2〜8抜き・北抜きあり・牌山108枚)は確率のバランスが大きく変わります。
- 連続ラス
ヨンマより発生しやすい。ラス率が25%から33.3%に増えるため、3連続ラスでも27回に1回と、日常的に遭遇するレベル。 - トップ不在の連続
数字上はヨンマの方が確率は高いが、サンマは「トップを取らないと順位点で勝てない」ルールのため、体感的には不運度が強烈。特に雀魂は +30/0/-30 の順位点なので「トップが遠い日=負けている日」になりやすい。 - 裏ドラ不発
ヨンマより若干「乗りやすい」ものの、依然として単発不発は約6割。南場4局連続で空振りする確率も約12.5%と、普通にあり得る範囲。
結論として、サンマは「不運が凝縮して起きやすい」ゲーム設計です。ラス率は上がり、トップの価値は重く、裏ドラは平然と外れる。だからこそ「今日は呪われている」と思うよりも、「この確率なら誰でも踏む」と理解することが大切です。不運のせいでメンタルが乱れ、打ち方を崩してしまうことこそ最大のリスクです。
確率を知っていれば、「3連ラスは27回に1回なら仕方ない」「南場で裏が全部外れるのも10%以上あるのだから当然」と受け止められます。その冷静さが次局の判断を守り、長期的な成績の安定につながります。
――サンマは荒れる。けれど荒れるのは、運に翻弄されているからではなく、ゲームの構造そのものがそうなっているだけ。確率を味方にすれば、不運に見える一日も「想定内」で済ませることができるのです。