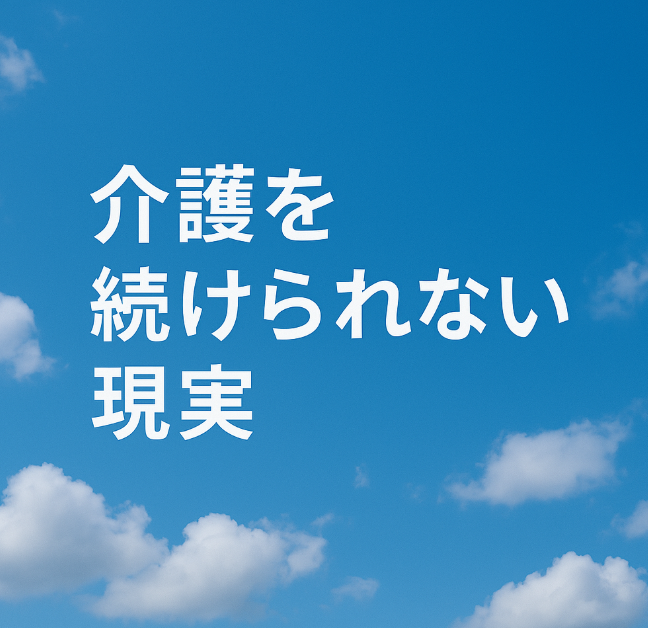釧路で、高齢の父親を放置したとして娘が逮捕されたというニュースを見ました。
父親は介助が必要な状態で、娘は「できることはしていた」と話しているそうです。

仕事をしながら介護を続けるのは、想像以上に過酷です。
お金、時間、体力、心――すべてが削られていく中で、
「ちゃんとしなきゃ」と自分を追い込み、気づけば限界を超えていたのではないでしょうか。
ニュースを読んで思ったのは、「誰も助けてもらえなかったんだな」ということ
釧路のニュースを見たとき、最初に浮かんだのは「この人は、どこにも頼れなかったんだろうな」という思いでした。
娘さんは派遣で働いていて、生活に余裕があったとは考えにくい。
それでも同居して、介護をしていた。
そしてあるとき、何かが限界を超えてしまった。
報道では「放置」と書かれていましたが、その言葉には違和感があります。
介護というのは、手を抜くとか放置するという単純な話ではないんです。
「今日はもう立たせるのが無理」と思っても、
「買い物に行く気力がない」と感じても、
そのどれもが責められるような言葉で片づけられてしまう。
多くの人が、できることはしていたと感じながらも、
実際には誰の助けも得られず、静かに追い詰められています。
介護を続ける中で、自分の生活も、感情も、仕事も壊れていく。
それでも「家族なんだから」という一言で、社会からの支援は途切れる。
あの娘さんも、きっと何度も「もう無理」と思いながら、
「まだ頑張らなきゃ」と自分を責めていたのではないでしょうか。
事件として報じられるときには、その過程は消えてしまいます。
でも、こうした誰も助けてもらえなかった物語は、
日本中のどこかで今も静かに起きているはずです。
介護は「やさしさ」だけで続けられるものじゃない
介護というと、どうしても「家族の愛情」や「優しさ」が前提に置かれがちです。
もちろんそれは大切な気持ちですが、現実はその想像よりずっと重く、長いものです。
やさしさだけでは、毎日をまわしていけません。
日々の食事、入浴、排泄、病院の付き添い。
一つひとつは「たいしたことない」と思えても、積み重なると、
まるで砂袋を抱えて暮らすような重さになります。
少し体調を崩しただけで予定が崩れ、
仕事を早退すれば、今度は職場の視線が気になる。
そんな綱渡りのような日々を、何年も続けている人がたくさんいます。
介護を担う人の多くは「自分がやるしかない」と考え、
制度を使わず、家族の中だけで抱え込んでしまう。
なぜなら、支援の窓口に行く時間も気力も残っていないからです。
「介護離職防止」とか「地域包括ケア」など、
国の方針は聞こえてくるけれど、
実際に支援が届くまでの道のりは長く、複雑で、説明も難しい。
たとえ制度を知っていても、
「他にもっと大変な人がいる」と遠慮してしまう人も少なくありません。
まとめ:生き方と終わり方を支える社会へ
釧路のニュースをきっかけに書き始めたこの記事でしたが、
改めて思うのは、誰も悪くないのに、悲しい結末を迎えてしまう現実があるということです。
介護も、病も、老いも、人の生の一部です。
現実問題として、介護しようにも給料的、時間的に無理がある方は絶対にいます。
というか余裕のある方の方が少ないでしょう。
しかるべき相談機関、親族、近隣の方に相談したとして、金銭的、時間的に援助がいただけるのか。
機関がどれだけ助けてくれるのか、そして、自分の家族以外の方のフォローまで生活に余裕がある方がどれだけいるでしょうか。
最近は外国人を優遇するニュースが多いですが、まずはこういう詰んでしまった状態の方を国が率先して守ってもらいたいと思いますね。