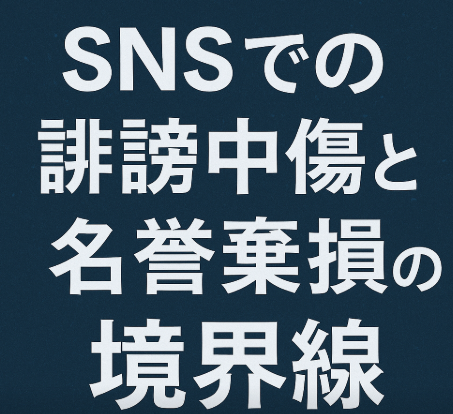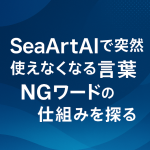SNSが日常の一部となった現代では、誰もが気軽に意見を発信できるようになりました。便利で自由な場である一方、その言葉が思わぬトラブルを招くことも少なくありません。特に、相手を傷つける投稿や根拠のない批判が「誹謗中傷」や「名誉棄損」と見なされ、法的責任を問われるケースが増えています。
近年では、匿名での発言であっても投稿内容から個人が特定されることがあり、警察による捜査や損害賠償請求につながる事例も報告されています。SNSは私的なつぶやきであっても不特定多数の人の目に触れる「公共の場」であることを意識する必要があります。
一方で、社会問題や公共性のある話題について正当な意見を述べることは表現の自由として守られています。そのため、何が「意見」で何が「誹謗中傷」なのか、その境界を正しく理解することが大切です。
この記事では、SNS上で名誉棄損や誹謗中傷にあたる可能性のある表現や、アウトになる具体的なケース、さらにトラブルを防ぐための注意点や被害時の対応までを、初心者にも分かりやすく整理して解説します。
SNSで誹謗中傷や名誉棄損が問題となる背景
SNSの登場により、個人が簡単に情報を発信できるようになりました。以前であればメディア関係者や一部の著名人しか広く意見を伝えられませんでしたが、今では誰でも数百、数千人に届く影響力を持つことが可能です。その一方で、軽い気持ちで投稿したコメントが相手を傷つけたり、名誉を損なったりするケースが急増しています。
また、SNSでは感情的な発言が目立ちやすく、短文形式や即時投稿という仕組みが誤解や炎上を生みやすい構造を持っています。たとえば「〇〇は詐欺だ」「あの人は最低だ」といった断定的な表現は、事実に基づかない場合、名誉棄損罪や侮辱罪の対象となる可能性があります。本人にその意図がなくても、受け手や第三者の解釈次第で法的問題に発展することがあるのです。
近年では、芸能人やインフルエンサーだけでなく、一般の個人間でも名誉棄損による訴訟や開示請求が増えています。SNSは身近な存在であるがゆえに、「軽い発言」でも法的責任を問われることを忘れてはいけません。
名誉棄損・侮辱・業務妨害の違いを理解する

SNS上で問題になる暴言や投稿には、複数の法律が関係します。代表的なのが「名誉棄損罪」「侮辱罪」「業務妨害罪」です。どれも他人の権利や社会的評価を守るための規定ですが、成立する条件や対象となる行為には明確な違いがあります。
名誉棄損罪が成立する要件
名誉棄損罪(刑法230条)は、他人の社会的評価を下げるような「事実」を公然と示した場合に成立します。ポイントは「事実の摘示」があるかどうかです。たとえば「A社の製品は欠陥だらけ」「Bさんは不倫している」といった投稿が、もし事実無根であれば名誉棄損となる可能性があります。
ただし、例外もあります。刑法230条の2では、公共の利害に関する事実であり、公益目的が認められ、なおかつそれが「真実」である場合には、名誉棄損罪が成立しないと定められています(参考:e-Gov法令検索・刑法第230条)。つまり、社会的に意義のある情報を正確に伝える目的であれば、一定の範囲で表現の自由が保護されるのです。
侮辱罪の適用範囲と最近の改正点
侮辱罪(刑法231条)は、事実を述べなくても相手を侮辱する言葉を公然と発した場合に成立します。たとえば「バカ」「無能」などの人格を攻撃する発言や、投稿に悪意あるあだ名をつける行為などがこれにあたります。
虚偽情報や誤解による業務妨害
さらに、企業や団体を狙った虚偽の口コミや風評が広がった場合、「偽計業務妨害罪」や「威力業務妨害罪」(刑法233条・234条)に該当することがあります。たとえば「この飲食店は食中毒を起こした」「この会社は倒産寸前だ」といった根拠のない投稿が業務に影響を与えた場合、刑事責任を問われる可能性があります。
このように、SNSでの発言は単なる「意見」ではなく、法的責任を伴う行為として扱われます。特に拡散力の高い投稿や匿名アカウントでの誹謗中傷は、本人が想定する以上の影響を及ぼします。
SNSで「アウト」になる表現の具体例

具体的な人物を指す投稿
最も典型的なのは、特定の人物や企業を名指しした投稿です。たとえば「○○社の社長は横領している」「△△さんは詐欺師だ」といった事実関係を伴う断定的な表現は、真実でない限り名誉棄損にあたります。また、名前を出さなくても「某有名ブロガー」「この写真の人」など、特定の人物が誰か推測できる内容であれば、法的に「特定可能性」があると判断されることがあります。
実際に、ある一般人がSNS上で他人を中傷する投稿を行い、被害者が発信者情報開示請求を行った結果、投稿者が特定され損害賠償を命じられた事例もあります(参考:東京地方裁判所令和2年判決)。このように匿名でも責任を逃れることはできません。
事実無根・過度な断定表現
「〇〇は最低」「あの人は犯罪者だ」「絶対に信用できない」など、感情的で断定的な表現も注意が必要です。特に「犯罪行為をしている」といった表現は事実の摘示にあたるため、証拠がなければ名誉棄損となる可能性が高いです。
また、誇張や比喩であっても文脈によっては誤解を招くことがあります。たとえば「この人は会社のお荷物」と書いた場合、読者がその人物の能力を疑うような印象を受ければ社会的評価を下げる行為と見なされることがあります。SNSは文脈が伝わりにくいため、冗談や皮肉のつもりでも危険です。
匿名でも特定できるケース
匿名アカウントでも、投稿内容から個人が特定されることがあります。勤務先や住んでいる地域、交友関係などの情報を組み合わせると、被害者や第三者が容易に誰を指しているのか推測できる場合が多いのです。
たとえば「同じ部署の上司が最悪」「うちのカフェの店長」など、限定的な範囲の中で個人を識別できる投稿は特定可能性があると判断されます。匿名性に安心して投稿しても、発信者情報開示請求によってプロバイダやSNS運営会社から情報が開示されることもあります。
こうした事例を見てもわかるように、SNSでは「誰かを傷つけるかもしれない言葉」はすべて公の場で発言しているという意識を持つことが大切です。
誹謗中傷と正当な批判の違い
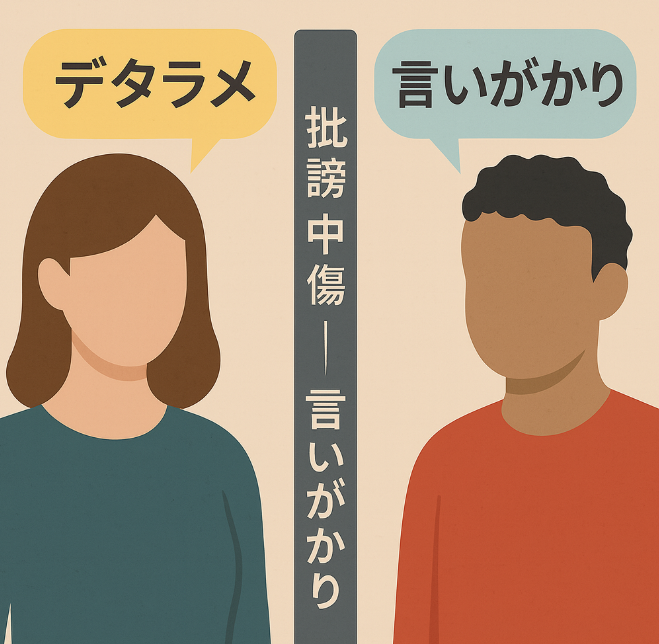
SNS上では、「批判しただけなのに誹謗中傷だと言われた」というトラブルが少なくありません。意見を述べる自由は誰にでもありますが、その表現方法を誤ると法的リスクを伴います。ここでは、誹謗中傷と正当な批判の違いを明確に整理します。
公共性・公益性がある場合の発言
社会的に意義のある事柄や公共性の高いテーマについて、事実をもとに意見を述べることは、原則として表現の自由として保護されます。たとえば「行政の対応が遅い」「企業の説明が不十分」といった発言は、公益性が認められる可能性があります。
ただし、その内容が真実であること、あるいは少なくとも「真実と信じるに足る相当な理由」があることが前提です。裏付けのない情報を断定的に発信した場合は、たとえ公益目的でも名誉棄損が成立することがあります。報道機関と同様に、個人がSNSで情報を拡散する場合も「事実確認の責任」を負うことを忘れてはいけません。
感情的な言葉がリスクを高める理由
正当な批判と誹謗中傷を分けるもう一つの重要なポイントは「表現のトーン」です。たとえば「説明が不十分だと思う」と述べるのと、「この会社は嘘つきだ」と言うのでは、受け取る印象がまったく異なります。
特にSNSでは、短い文章に強い感情を込めやすく、結果的に攻撃的な表現になりがちです。感情的な言葉や人格を否定する言い回しが加わると、それは「意見」ではなく「侮辱」と受け取られやすくなります。
また、相手の意見に反論する際も、相手の人格や存在そのものを否定する表現は避けるべきです。批判は「行為や発言」に向けるものであり、「人」に向けてはいけません。この区別を意識するだけでも、誤解やトラブルを防ぐことができます。
さらに、事実確認を怠ったり、他人の投稿を安易に引用・拡散したりすることも注意が必要です。根拠のない情報を拡散する行為は、自分が直接投稿していなくても名誉棄損の加害者として責任を問われることがあります。
つまり、批判と誹謗中傷の違いは「目的」と「方法」にあります。社会的に必要な意見を、冷静に根拠を示して伝えることができていれば、それは正当な批判と認められます。
SNS利用で気をつけたい予防策

SNSは手軽に発信できる反面、たった一言で取り返しのつかないトラブルを生むことがあります。ここでは、投稿する際に意識すべきポイントや、トラブルを未然に防ぐための実践的な対策を紹介します。
発信前にチェックしたい3つのポイント
1つ目は「事実確認」です。投稿する内容が事実に基づいているか、信頼できる根拠があるかを必ず確認しましょう。特に他人に関する情報は、ニュースや一次情報に基づいているかどうかが重要です。
2つ目は「表現のトーン」です。同じ内容でも、言葉遣いや語尾を変えるだけで印象は大きく変わります。たとえば「対応が遅いと思う」と「この会社はダメだ」は意味が異なり、後者は侮辱と見なされる可能性があります。感情的な投稿は一度下書きに保存し、冷静になってから読み返す習慣をつけましょう。
3つ目は「公開範囲の設定」です。フォロワー限定にしたつもりでも、スクリーンショットで拡散されることがあります。投稿後は完全にコントロールできないという意識を持つことが大切です。
匿名アカウントでも責任は問われる
匿名アカウントであっても、発信者情報開示請求によって投稿者が特定されるケースは珍しくありません。プロバイダ責任制限法に基づき、被害者はSNS運営会社や通信事業者を通じて発信者のIPアドレスや契約者情報を請求できます。裁判所の判断で情報開示が認められれば、匿名であっても身元は特定されます。
削除依頼や通報の正しい手順
もし自分が誤って他人を傷つける投稿をしてしまった場合は、速やかに削除し、相手への謝罪を検討することが望ましいです。また、誹謗中傷を受けた場合は、まずSNSの通報機能やブロック機能を活用しましょう。プラットフォームによっては、運営が内容を審査し、削除やアカウント停止を行うことがあります。
さらに、悪質な投稿が続く場合は、専門機関への相談も有効です。後述しますが、弁護士や公的機関に相談することで、削除要請や法的措置を取ることも可能です。
SNSを安全に使うためには、「誰が見ても誤解されない発言」を心がけることが何よりの予防策です。
被害を受けた場合の対応方法と相談先
SNSで誹謗中傷や名誉棄損の被害を受けた場合、感情的に反応してしまうのは自然なことですが、冷静な対応が最も重要です。削除要請や法的措置を適切に行うことで、被害を最小限に抑えることができます。ここでは、具体的な対応手順を段階的に説明します。
証拠の保存と専門機関への相談
まず最初にすべきことは、投稿内容の証拠を確保することです。相手が投稿を削除する前に、スクリーンショットを撮影し、URL・日時・投稿者名を記録しておきましょう。可能であれば、第三者が確認できる形で保存しておくことも有効です。
弁護士・警察・プロバイダへの対応フロー
誹謗中傷の内容が悪質で、精神的な苦痛や社会的損害が大きい場合は、弁護士を通じて「発信者情報開示請求」を行います。これにより、匿名投稿者の特定を求めることができます。特定後は、損害賠償請求や刑事告訴を検討します。
また、脅迫やストーカー行為に発展している場合は、迷わず警察へ相談してください。被害届を出す際には、証拠データが非常に重要です。さらに、SNSの運営会社やプロバイダに対して削除要請を行うことも有効です。削除が受理されれば、被害の拡大を防げます。
心のケアや支援団体の活用
誹謗中傷による精神的ダメージは非常に大きく、長期間にわたって苦しむ人も少なくありません。必要に応じて、心療内科やカウンセラーなど専門機関のサポートを受けることも大切です。
まとめ|SNS時代の発信に必要な意識
SNSは、誰もが自由に情報を発信し、他者と意見を交わすことができる便利なツールです。しかし、その自由には責任が伴います。わずか数十文字の投稿でも、相手の名誉や社会的評価を大きく傷つける可能性があり、法的責任を問われるケースも少なくありません。
この記事で見てきたように、名誉棄損罪や侮辱罪は「意図がなかった」としても成立することがあります。特にSNSは、感情的な言葉や断定的な表現が目立ちやすい環境です。発信者が想定する以上に多くの人が投稿を目にすることを常に意識し、「事実かどうか」「相手がどう受け取るか」を確認する習慣が大切です。
一方で、社会的な問題に対して意見を述べることは決して悪いことではありません。むしろ、公共性や公益性のある発言は、社会を良くする力を持っています。ただし、そのためには冷静で根拠ある言葉を選び、相手を尊重する姿勢を忘れないことが必要です。
また、誹謗中傷の被害を受けた場合には、専門機関や法的支援を積極的に活用することが重要です。個人では解決が難しい問題も、相談機関や専門家のサポートによって前進することができます。