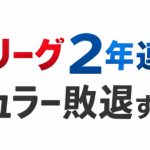知的障害で冤罪を背負わされた世界一幸せな死刑囚と呼ばれ、死刑に至った人物がいます。
その人物が ジョー・アレディ です。重度の知的障害を抱えた彼は、警察の取り調べで虚偽の自白を行ったとされ、十分な検証がなされないまま有罪判決を受け、最終的に死刑が執行されました。後年になって冤罪の可能性が指摘され、死後恩赦が与えられたことで、この事件は冤罪を語る際の代表的な事例として知られるようになります。
一方で、この事件は死刑制度そのものを否定する論拠として語られることも多くあります。しかし、個別の冤罪事件と、社会全体における死刑制度の是非は、同じ枠組みで論じるべき問題なのでしょうか。過去の司法制度が抱えていた欠陥と、現在の捜査や証拠の精度をどう切り分けて考えるべきかという点も含め、慎重な整理が求められます。
本記事では、事件の概要を押さえた上で、知的障害と冤罪が結びついた背景を整理しながら、冤罪の存在を前提とした場合に死刑制度をどう考えるべきかを検討していきます。
世界一幸せな死刑囚
世界一幸せな死刑囚と呼ばれる人物は、アメリカ合衆国コロラド州で無実の罪により処刑された ジョー・アレディ です。1915年に生まれた彼は、幼少期から重度の知的障害があり、知能指数はおよそ46、精神年齢は5から6歳程度と評価されていました。成長後も自立した生活は難しく、州立学校の施設で生活していたことが知られています。

事件の発端は、1930年代に起きた15歳の少女殺害事件でした。世論の強い圧力を受けた警察は早期解決を求められ、施設を抜け出して放浪していたアレディを逮捕します。取り調べの過程で彼は犯行を認める供述をしましたが、その内容には事実と合わない点が多く含まれていました。後に別の男が単独犯行を自白しているにもかかわらず、この供述は十分に再検証されませんでした。
知的障害を抱えていたアレディは、質問の意味を正確に理解することが難しく、警察官の誘導に同調しやすい状態にあったとされています。供述内容は取り調べの過程で修正され、別の容疑者を含める形に変えられたとも指摘されていますが、当時はその信頼性が厳しく問われることはありませんでした。このようにして形成された自白が、裁判における主要な証拠として扱われることになります。
1939年、アレディは23歳でガス室による死刑を執行されました。処刑の意味を十分に理解していなかったとされる彼の振る舞いは、後年になって幸せという言葉を伴って語られる要因の一つとなります。2011年には、虚偽の自白や犯行時に現場にいなかった可能性などが認められ、死後に完全かつ無条件の恩赦が与えられました。この経緯から、彼の事件は冤罪と知的障害、そして死刑という問題を考える際の象徴的な事例として扱われています。
知的障がい者に対する取り調べの問題点
この事件で最も大きな問題とされているのは、自白の扱われ方です。取り調べで引き出された供述は、犯行内容に不正確な点が多く含まれていましたが、その矛盾が十分に検証されることはありませんでした。知的障害を抱えていた被疑者が、質問に合わせて肯定的な返答をしてしまう可能性についても、当時の捜査では深く考慮されていませんでした。
裁判においても、自白の位置付けは極めて重いものでした。弁護側は知的障害や供述の信頼性に問題があることを主張しましたが、裁判所が任命した弁護士は有罪を前提とした対応を取り、防御活動は限定的だったとされています。その結果、物的証拠や第三者の供述との整合性について、十分な審理が行われないまま有罪判決が下されました。
また、事件後に別の人物が単独犯行を自白していた事実も、裁判では決定的に扱われませんでした。世論の圧力の中で早期解決が求められていた状況もあり、捜査や裁判が慎重さを欠いたまま進んでしまったことが、この冤罪を固定化させた要因の一つと考えられています。
知的障がい者による冤罪事件はほかにも
まず、イギリスで起きたエヴァンス事件です。1949年、妻子を殺害したとして逮捕された ティモシー・ジョン・エヴァンス は、軽度の知的障害と言語障害を抱えていました。取り調べでは警察の誘導による自白が重視され、有罪判決を受けて死刑が執行されます。しかしその後、同じアパートに住んでいた別の男が連続殺人犯であったことが判明し、エヴァンスの冤罪が明らかになりました。この事件は、後にイギリスで死刑廃止が進む過程で議論の的となります。
次に、日本で起きた島田事件です。1954年、6歳の女児が殺害された事件で、島田成人が逮捕、起訴され、死刑判決を受けました。島田も知的障害があるとされ、取り調べでは自白が中心的証拠として扱われました。後年、供述の信用性や捜査手法に重大な問題があったことが指摘され、再審で無罪が確定しています。この事件は、日本における冤罪と取り調べの問題を象徴する事例として知られています。
これら二つの事件はいずれも、知的障害や供述の扱いが冤罪につながった点で共通しています。一方で、国や時代、制度の違いにもかかわらず、冤罪が社会的に大きな影響を与えた事例として語られてきました。
冤罪と死刑廃止論
冤罪事件が死刑廃止論と結びついて語られる際、まず強調されるのは個別事件の悲劇性です。無実である可能性の高い人物が処刑されたという事実は、それだけで強い衝撃を持ち、制度全体への評価を一気に引き下げる力を持ちます。しかし、この時点では、個別の事件で何が起きたのかと、死刑制度が社会においてどのような役割を担っているのかは、切り分けて考えられていません。
次に起きやすいのが、制度の一般化です。複数の冤罪事件が示されることで、冤罪が起きた原因が個別の捜査や裁判の問題であったにもかかわらず、死刑制度そのものが必然的に冤罪を生む制度であるかのように語られるようになります。ここでは、運用の失敗と制度の存在意義が同一視されがちです。
さらに、不可逆性という性質が議論を強く押し進めます。死刑は取り消すことができない刑罰であるため、一度でも冤罪が確認されれば制度全体が許されないものだという論理が成立しやすくなります。この論理は直感的には理解しやすいものですが、他の刑罰や司法制度全体が抱える誤判の可能性との比較が省略されやすいという特徴も持っています。
最後に、感情の強さが結論を先に固定してしまう点があります。冤罪事件では、弱い立場に置かれた被疑者や処刑後の事実判明が強調されるため、議論は道徳的評価に傾きやすくなります。その結果、抑止力や被害者側の視点といった要素が十分に検討されないまま、廃止か存続かという二者択一に収束していきます。
冤罪と死刑制度の是非
冤罪が起き得る以上、死刑制度は認められないという考え方は、一見すると合理的に見えます。しかし、冤罪の可能性があるという事実と、死刑という刑罰が社会にとって必要かどうかという問題は、同一の次元で扱うべきものではないと思っています。私は死刑肯定派です。
死刑が必要だと考える理由の一つは、凶悪犯罪に対する抑止力の存在です。すべての犯罪を防げるわけではないとしても、最も重い刑罰が制度として存在していること自体が、一定の歯止めとして機能しているという考え方ですね。統計上そうではないデータも出ているそうですが、抑止力として踏みとどまる人間はゼロではないと思っています。
また今回は知的障害と冤罪の話ですし、すべての事件に対してそう思ってるとは言えないのですが、現在の死刑になるような凶悪犯罪を意図して起こした人間が死刑になるのは当然だと思ってますし、正直死刑にならないのが納得できない事件もよく目にします。
私は犯罪被害者ではないですけど、犯罪被害者から見たらせめて死刑にって思う事件も多いと思います。
まとめ
本記事では、知的障害で冤罪を背負わされた世界一幸せな死刑囚と呼ばれる事件を起点に、冤罪と死刑制度がどのように結びついて語られてきたのかを整理してきました。
恐らく今回のように社会的弱者が押し付けられた冤罪はたくさんあるんだろうと思いますね。それでも私は死刑は必要だと思います。