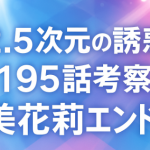原神を遊んでいると、物語の各国を巡るたびに壮大な世界観や人々の思いに触れることができます。その中でも常に中心にいるのが、プレイヤー自身が操作するキャラクター「旅人」です。主人公でありながら、彼(または彼女)の正体については長い間ベールに包まれたまま。なぜ神の目を持たずに元素を操れるのか、なぜ天理に拒絶されて兄妹と分かたれてしまったのか──物語の根幹に関わる疑問は、プレイヤーの心を強く惹きつけています。
旅人の正体を探る手がかりは、ゲームの随所に散りばめられています。例えば、スメールで占い師に寿命を見られた際に「何万年も先」と驚かれるシーン。これは人間どころか神の寿命すら超える存在であることを示唆しており、彼らが“テイワットの住人ではない”ことを裏付けています。また、旅人はビジョンを介さず七天神像と共鳴して元素を切り替えられる唯一の存在であり、この仕組みもテイワットの理から外れていると考えざるを得ません。
さらに物語が進むにつれ、「降臨者」という概念が語られるようになりました。旅人がその一人であることは明らかで、冒頭で天理に拒絶された出来事とも深く関わっています。つまり、旅人はただの異邦人ではなく、“世界の外から来た者”として、テイワットに揺らぎをもたらす存在なのです。

このように考えると、旅人の正体は単なる出生の秘密ではなく、原神という物語全体を理解するうえで避けて通れないテーマだと言えます。兄妹とのすれ違いや、各国で出会う神や人々との関わりはすべて「世界に属さない者」としての立場を際立たせています。そしてその立場が、今後の物語の結末を大きく左右することになるでしょう。
旅人の正体をめぐる謎──原神の物語における立ち位置
原神をプレイしていると、旅人は常に物語の中心にいながらも「何者なのか」がはっきり示されないことに気づきます。モンドでの出会いから璃月や稲妻、スメール、フォンテーヌを経てナタへと進んでも、彼(または彼女)の正体は断片的な情報でしか語られません。プレイヤーは旅人として世界を歩き、多くの人々と関わりながらも、主人公自身の背景は謎のまま残されているのです。

この正体の不明瞭さは、原神という作品において重要な仕掛けになっています。一般的なRPGでは、主人公の出自や役割が序盤で明確に示されることが多いですが、原神の場合はあえてそれを隠し続けることで「プレイヤーが世界に没入していく感覚」を強めています。プレイヤーは旅人と同じく記憶の一部を失った状態から冒険を始め、各地で断片的な情報を集めながら真実に近づいていく。この体験そのものが、旅人の正体を探るプロセスに重ねられているのです。
物語の冒頭から、旅人が「テイワットの外」から来た存在であることは示唆されています。兄妹が「いくつもの世界を旅してきた」と語る場面は、その最たる証拠です。これはただの幻想的な表現ではなく、実際に彼らが複数の世界を渡り歩いてきたことを意味しています。つまり旅人は、テイワットという世界の内部ではなく、外部からやってきた来訪者であり、この世界の理に従う必要のない特異な存在だということです。
この点が強調されるのは、他のキャラクターたちとの対比においてです。テイワットの人々は「神の目」によって元素を操ります。七神と呼ばれる神々は「神の心」を通じて世界と結びついています。竜やアビスといった異質な存在も、それぞれ独自の理に縛られています。しかし、旅人だけはそのどれにも属さず、それでもなお元素を扱い、世界の根幹に触れることができるのです。この構図は、旅人がテイワットのルール外に立っていることを際立たせます。

また、旅人が兄妹と引き裂かれる冒頭のシーンも象徴的です。天理の調停者によって分断され、一人は眠りにつき、もう一人はすでにこの世界を歩んでいた。この出来事は、旅人が「管理者によって排除されるべき存在」と認識されていることを示唆しています。つまり天理から見れば、旅人はテイワットの理に従わない危険な存在であり、システム外からの“侵入者”に近い位置づけだったのです。
ただし、旅人は単なる異物ではありません。各地で人々と出会い、神々と関わり、アビスや竜の脅威に立ち向かう中で、彼らは「観測者」としての役割を果たしています。世界の外から来たからこそ、この世界の内部では見えない矛盾や歪みを発見でき、それに干渉することができる。旅人は「外部にいるがゆえに中を理解できる存在」であり、この立ち位置こそが正体の核心にあるといえるでしょう。
神の目を持たない旅人が元素を操れる理由
原神の世界に生きる人々にとって、元素の力を操るには「神の目」が不可欠です。神の目は神々から選ばれた者に授けられる外部装置であり、それを持つことで初めて炎や水、雷といった元素を行使できるようになります。璃月の人々が語るように「神の目は神明からの承認」であり、持つこと自体が名誉とされています。しかし、旅人は神の目を一切持たずに元素を操ります。しかも、モンドでは風、璃月では岩、稲妻では雷、スメールでは草、ナタでは炎と、複数の元素を切り替えることが可能です。この点は、彼らの正体を考える上で最も特異な要素のひとつです。
では、なぜ旅人だけが神の目を必要としないのでしょうか。ひとつの仮説は、旅人が「元素そのものに直接接続できる構造」を持っているというものです。テイワットの住人は神の目を媒介にして元素力に触れますが、旅人は七天神像に祈ることで新たな元素を解放できます。これは「誰かに与えられた力」ではなく、「封印されていた自身の能力を思い出している」かのようなプロセスです。実際に旅人が「力が戻ってきた気がする」と語る場面もあり、もともと内包していた力を再び取り戻していると解釈できます。
さらに注目すべきは、旅人の元素切り替えが「選択ではなく適応」に近い点です。通常、神の目を持つ者はひとつの元素にしか適応できません。たとえば炎の神の目を持つキャラクターが水や氷を操ることはできません。しかし旅人は環境に応じて複数の元素を扱い分けられます。これはテイワットの既存ルールとは明らかに異質であり、「世界の根源的な記憶やエネルギー」に直接アクセスしているように見えます。
この特性は、旅人がアビスや竜といった存在に干渉できる理由とも繋がっています。モンド編ではアビスに蝕まれたトワリンに近づくだけで旅人の存在が浄化のきっかけとなり、ナタ編では竜化の暴走を抑えるような反応を示しました。これらは単なる戦闘力の問題ではなく、旅人が「世界の理そのもの」に干渉できる構造を持つことの証明だと考えられます。神の目に依存せず、根源にアクセスすることができるからこそ、通常の住人が不可能な作用を生み出せるのです。

また、この「神の目を必要としない」という特徴は、旅人がテイワットの外から来た存在であることを裏付けます。神の目はこの世界のシステムに属する者に与えられる“内部認証キー”のようなものです。もし旅人が外部から来た存在であれば、そのキーを発行されることはなく、代わりに“外部接続者”として直接アクセスする権限を持っていると考える方が自然です。つまり、旅人の力の本質は「特別な祝福」ではなく「外部起点の権限」に近いのです。
天理と旅人の関係──なぜ世界に拒絶されたのか
原神の冒頭で描かれた、旅人と兄妹がテイワットに降り立った瞬間の出来事は、多くのプレイヤーに強烈な印象を残しました。突如現れた光の存在によって行く手を阻まれ、二人は引き裂かれてしまう。その存在は「天理の調停者」と名乗り、旅人を力で封じ込めようとしました。この出来事は、旅人がこの世界に歓迎されない存在であることを象徴しています。ではなぜ、天理は旅人を拒絶したのでしょうか。
まず考えられるのは、天理の役割です。七神が国を治めているとはいえ、彼らでさえ「神の心」を天理から授かっているに過ぎません。つまり、テイワットの秩序そのものは天理によって維持されており、七神も例外なくその支配下にあります。もしテイワットという世界をシステムに例えるなら、七神は管理者に近い立場ではあるものの、最終的な制御権限は天理が握っているのです。

この視点から見ると、天理にとって旅人は「未登録の外部データ」のような存在だったと考えられます。ナヒーダが語ったように、旅人は「世界樹に記録されていない」=この世界の歴史やデータに存在しない例外的な存在です。世界の基盤を守る天理にとって、記録されない者が内部に干渉することは極めて危険であり、システムを破壊しかねない。だからこそ、冒頭で旅人と兄妹を分断し、封じ込めるという行動に出たのだと解釈できます。
重要なのは、天理の行動が必ずしも「敵意」から出たものではないという点です。むしろそれは秩序を守るための自動防衛のようなものでした。世界に属さない存在を排除することは、秩序維持の観点から見れば自然な動きです。しかし、旅人は完全に消去されることなく記憶と力を失った状態で目覚め、再びテイワットを歩み始めます。この事実は、天理が万能ではなく、例外を完全に制御できなかったことを意味しています。
この「制御の限界」は、フォンテーヌ編でも垣間見えました。正義を司るシステムが旅人たちの行動によって欺かれる場面は、天理の支配が絶対ではなく、あくまで「ルールに基づく管理」に過ぎないことを示しています。つまり天理は神々を超える存在ではあるものの、無限の知識と力を持つ全能神ではなく、あくまで「秩序維持プログラム」のような存在だと考えられるのです。
旅人が天理に拒絶された理由をもう一歩掘り下げると、「旅人はこの世界を書き換える可能性を持つ存在だから」という点に行き着きます。テイワットに属する神や人間は、それぞれが決められたルールに従って生きています。神の目を介して元素を扱い、寿命の枠に縛られ、神の心を持って国を治める。すべては天理が定めた秩序の範囲内です。しかし旅人はそのどれにも属さず、外部から来た者として「ルール外の権限」を持っています。その存在が秩序を脅かす可能性がある以上、天理にとって封じるしかない対象だったのです。
とはいえ、旅人はただの異物ではなく、世界を観測し変化を与える「外部の変数」として物語に組み込まれています。天理が世界を安定させるためのシステムであるのに対し、旅人は外部から刺激を与える例外的存在。両者は根本的に対立する立場にありながらも、どちらも物語の進行には欠かせない役割を担っているといえるでしょう。
結局のところ、天理が旅人を拒絶したのは「危険だから」ではなく、「秩序維持のために想定外を排除せざるを得なかったから」と解釈するのが自然です。そして、完全には排除できなかったがゆえに、旅人は記憶を失った状態で物語を歩き続けることになりました。この関係性は、原神の物語全体を通じて「秩序と例外」「管理と自由」というテーマを際立たせる重要な要素になっています。
兄妹が歩んだ異なる道と旅人の記憶の断片
原神の物語において、旅人の正体を考えるうえで避けて通れないのが「兄妹の存在」です。プレイヤーが操作する旅人は、双子のうち一方であり、もう一方は物語開始直後に天理の調停者によって引き裂かれ、別の運命を歩むことになりました。この兄妹の分断こそ、原神のストーリーの根幹にあるテーマであり、旅人の正体や役割を理解するための重要な要素です。

物語冒頭、旅人と兄妹は「いくつもの世界を旅してきた」と語っています。これは、彼らがテイワット以前にも複数の世界を渡り歩いていたことを意味しており、人間や神々とは異なる次元の存在であることを裏付けています。けれどもテイワットに降り立った瞬間、天理の力によって二人は引き離され、一方は眠りにつき、一方は先にこの世界を巡る旅を続けることになりました。ここで分かれた道が、その後の物語に大きな影響を与えていきます。
プレイヤーが操作する旅人は、記憶と力を失った状態で目覚めます。彼らは世界を歩く中で少しずつ力を取り戻し、同時に過去の断片的な記憶を思い出していきます。しかしその記憶は不完全で、兄妹と共に歩んだ旅のすべてを思い出せるわけではありません。あえて欠落した記憶のままにされている点は、物語全体を通じてのミステリーの核であり、読者やプレイヤーに「この世界の真実はどこにあるのか」という問いを突きつけています。
一方、先に旅を続けていた兄妹は、全く異なる選択をしました。ダインスレイヴが語るように「君の兄(または妹)は、この世界のすべてを見た」。七国を巡り、神々を目にし、人々の希望や絶望に触れた結果、兄妹はアビスの王子/姫という立場に身を置きます。これは「旅を終えた者」としての選択であり、「世界を信じる」か「世界に抗う」かという二つの道が兄妹の間で分かれてしまったことを示しています。
この非対称性は、プレイヤーに強い印象を与えます。記憶を失いながらも再び旅を始めた旅人と、記憶を保ったまま世界を見て絶望した兄妹。二人は同じ存在でありながら、異なる視点から世界を見て、それぞれ違う答えにたどり着きました。旅人が「再び信じてみたい」と歩みを続ける一方で、兄妹は「抗わなければならない」としてアビスに加担する。この構図は「選択」というテーマを象徴しています。
さらに注目すべきは、二人が敵対しているわけではないという点です。再会の場面では、確かに緊張感や距離感はありますが、そこには憎しみではなく「理解できない道を歩む相手への戸惑い」が描かれています。兄妹は互いを失っていないし、完全に決別したわけでもない。だからこそ、旅人の旅は「過去を思い出す旅」であると同時に、「再び同じ未来を選ぶための旅」でもあるのです。
また、兄妹の物語は「記憶」というモチーフとも深く結びついています。旅人が失った記憶は、単なる情報ではなく「選択の理由」そのものです。なぜ兄妹は異なる道を歩むことになったのか。なぜ一方は絶望を選び、もう一方は希望を追うのか。その答えは、旅人が取り戻す記憶の中に隠されています。世界樹が「外部から来た者を記録しない」とされる設定も、こうした記憶の欠落やねじれを物語的に支える仕掛けになっています。
最終的に、兄妹の分断は「この世界をどう見るか」という問いに収束します。兄妹はどちらも間違っていないし、どちらも正しいわけではありません。旅人が歩む旅は、兄妹の選択を理解しつつ、自らがどんな未来を選ぶかを決めるための過程なのです。再会はゴールではなく、新たな選択の出発点。その意味で兄妹の物語は、旅人の正体の謎を解き明かすと同時に、原神という物語の最大のテーマを体現しているといえるでしょう。
降臨者(ディセンダー)としての旅人──記録されない存在の意味
原神のストーリーを語るうえで欠かせない概念のひとつに「降臨者」があります。これは、テイワットの外からやって来た存在を指す言葉で、旅人がその一人であることはほぼ確定的に語られています。重要なのは、降臨者はテイワットの歴史を蓄える世界樹に「記録されない」存在だという点です。この特性が、旅人の正体を考えるうえで決定的な意味を持っています。

世界樹は、テイワット全体の出来事や人々の記憶を保持する巨大な情報ネットワークのようなものです。スメール編では、そこから特定の記録が削除されることで、人々の記憶が書き換えられる描写がありました。つまり、世界樹に記録される=この世界に存在した証拠が残るということです。しかし、降臨者はそこに記録されない。言い換えれば、彼らは「世界のデータベースに存在が残らない例外的な存在」であり、理論上は“いなかったこと”にされてしまうのです。
この特性が旅人の正体とどう関わるのでしょうか。まず、記録されないということは、彼らが「テイワットの理そのものに属していない」ことを意味します。人間は寿命や歴史によって記録され、神々も神の心を通じて世界と結びついています。アビスや竜といった存在ですら、何らかの形で記録の中に痕跡を残します。ところが旅人は、そのどれにも当てはまらない。外部からやって来た者として、根本的に記録の仕組みの対象外にあるのです。
これは単なる設定的な特徴ではなく、物語上の意味を強く持っています。旅人が「記録に残らない存在」であるからこそ、天理によって拒絶され、兄妹と引き裂かれたと考えることができます。世界を管理する立場からすれば、記録されない存在は秩序にとって最大の不確定要素です。削除も制御もできない以上、封じ込めるしか方法がなかったのです。
また、旅人が世界樹に記録されないことは、記憶や歴史と密接に関係しています。旅人が自分の過去を完全には思い出せないのは、記録そのものが存在しないからだと解釈できます。普通のキャラクターであれば、歴史の痕跡を辿ることで真実に近づけますが、旅人の場合は“データが初めからない”。だからこそ、旅を進めながら新たな記憶を紡ぎ、兄妹との再会を通じて自らの物語を再構築する必要があるのです。
降臨者という立場は、旅人に特別な力を与える根拠にもなっています。神の目を持たずに元素を操れるのも、既存のルールに属さないからこそ可能だといえます。七天神像に触れることで元素を切り替えられる仕組みも、内部の法則に縛られていない外部者だからこその現象です。さらに、アビスや竜といった“世界の亀裂”に干渉できるのも、降臨者という枠外の存在だからこそ説明がつきます。
プレイヤーにとって興味深いのは、降臨者が旅人だけではない可能性です。ストーリー中では「降臨者は四人いる」と示唆されています。旅人とその兄妹がそのうちの二人だとすれば、残りの二人は誰なのか。そして、彼らが記録されない存在としてどのように物語に関わってくるのか。これも原神の大きな謎の一つであり、今後の展開で解き明かされることが期待されています。
総じて、降臨者としての旅人は「世界の外から来た例外」であり、「記録に残らない存在」であるがゆえに、物語の中心に立ち続けています。この設定は、単なる主人公補正ではなく、世界観そのものを揺るがす要素として描かれているのです。旅人の正体を考える上で、降臨者という概念は避けて通れない鍵であり、彼らが何を選ぶかによって原神という物語そのものの未来が決まるといえるでしょう。
旅人の力が物語に与える影響と今後の展開
旅人の正体を考えるとき、外部から来た降臨者という立場や神の目を持たずに元素を扱える特異性に注目が集まりがちです。しかし、もうひとつ見逃せないのが「その力が物語全体にどう影響しているのか」という点です。旅人の力は単なる戦闘能力を超えて、原神という物語の進行やテーマに直結しています。そして、その先にある展開予想も、彼らの正体と密接に結びついています。
まず、旅人の力が特異なのは「存在しているだけで環境に作用する」場面があることです。モンドでアビスに蝕まれたトワリンに接近すると、旅人の存在そのものが浄化のきっかけとなりました。通常なら七神や特定の力によって解決されるはずの問題に、旅人が触れるだけで状況が変化する。これは、彼らがテイワットの内部ルールに従う存在ではなく、外部的な干渉者であることを示しています。
ナタ編でもこの構造は顕著です。竜が暴走する場面で、旅人は力でねじ伏せるのではなく「共鳴」や「抑制」といった働きを見せました。これは攻撃力や元素反応といった既存の仕組みでは説明できず、旅人が「存在論的に異なる立場」にいるからこそ可能になった作用です。こうした描写は、旅人の力が「神や人間の延長線上にある力」ではなく「外部権限として世界を操作する力」であることを強調しています。
この力は、物語上で大きな二つの意味を持ちます。ひとつは「世界を癒やす可能性」。旅人がアビスの穢れや竜の暴走に干渉できることは、世界の矛盾や破綻を修復できる力として描かれています。プレイヤーにとっても、この“癒やしの象徴”としての旅人像は共感を呼ぶポイントです。もうひとつは「秩序を揺るがす脅威」。天理が旅人を拒絶した理由も、この点に重なります。外部から世界を書き換えられる存在は、管理者から見れば最も危険な異物であるのです。
では、この力が今後の展開にどう関わるのでしょうか。ひとつの可能性は「天理との最終的な対峙」です。物語の冒頭で旅人を封じようとした天理は、今後も物語の根幹に立ちはだかる存在として描かれるでしょう。旅人が持つ「外部からの権限」は、天理にとって制御できない唯一の要素であり、それが最終局面で衝突することは避けられません。
もうひとつの展開は「兄妹との再選択」です。兄妹が歩んだ道は、旅人とは正反対でした。兄妹は世界を見て絶望し、アビスに身を置く選択をしました。一方、旅人は世界を信じ、再び未来を切り開こうとしています。この二つの道が交わるとき、旅人の力は「説得」や「共鳴」といった形で兄妹に影響を与える可能性があります。力で相手を倒すのではなく、外部からの干渉者として“選択をやり直す機会”をもたらすことこそ、旅人の役割かもしれません。
さらに、今後の展開で注目すべきは「降臨者は四人いる」とされる点です。旅人と兄妹以外に、残る二人は誰なのか。すでに登場しているキャラクターなのか、これから現れるのか。それによって、旅人の立ち位置や力の意味が大きく変わってくるでしょう。彼らが“世界樹に記録されない存在”としてどのように描かれるかは、原神のストーリーを理解するうえで重要な転換点になるはずです。
最後に、旅人の力がプレイヤーに与える意味について触れたいと思います。旅人は単なる主人公ではなく、プレイヤー自身の分身でもあります。だからこそ「外部から来た存在」という設定は、プレイヤーがテイワットという世界に干渉する立場と重なっています。神の目を持たずに元素を扱い、世界の矛盾に干渉できるのは、プレイヤー自身が外部から物語に参加しているからだとも解釈できます。これは、ゲームという媒体ならではのメタ的な仕掛けであり、旅人の正体が物語を越えてプレイヤー体験そのものと結びついている点は非常に興味深い部分です。
総合すると、旅人の力は「癒やし」と「脅威」の二面性を持ち、物語を揺るがす推進力となっています。そしてその行き着く先は、天理との対峙、兄妹との再会、そして残る降臨者の登場によって明らかになっていくでしょう。旅人の正体は、原神という物語の未来そのものを左右する存在であり、その力がどのように使われるのかが最大の見どころになるのです。